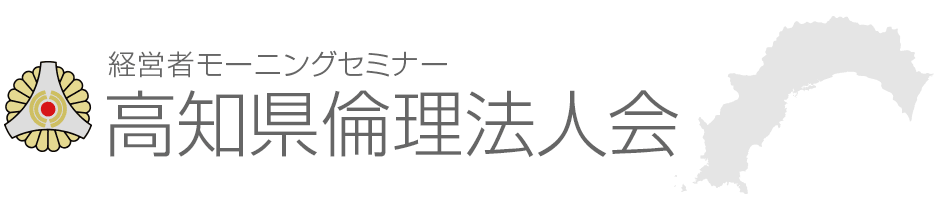合同役員研修「"日本創生"に資する倫理経営とその実践」が行われました。
■2014.02.25更新
平成26年2月5日、高知市のホテル日航高知旭ロイヤルにて、丸山敏秋理事長による合同役員研修「"日本創生"に資する倫理経営とその実践」が行われました。
最初に、久万田昌弘高知県倫理法人会会長より挨拶があった後、丸山理事長の講義が1時間あまり行われました。以下講義内容の抜粋です。

今年、平成26年は午年ですが、十二支では7番目になります。動物のウマのように駆け行く例えもありますが、本来は干支の後半に向かって伸び行く意味を込められているのだと思います。
昨年は八幡神社の中心である伊勢神宮と裏の中心である出雲大社、両方で御遷宮が行われました。これは60年に1度のことで、この重なった年には大きなことが起こるといわれています。60年前にはテレビ放送が始まりました。現在の日本も政局が変わり、空気が変わった感じがします。しかし、今年予定として決まっていることは、世界的にあまりありません。このことは逆に何が起こるかわからない不確定な時代と言えるでしょう。
現在、日本の国が抱える最大の課題は「少子高齢化」です。人口が減少していきます。これまでは、人口増に基づいて日本は動き、手厚い福祉政策がとられてきました。今後どうするのか、未だ有効な政策がありません。そんな中、個人としてできることは「自助努力」です。自分のことは自分でやる。健康でいることもその1つです。
純粋倫理の説く「実践」とは、自分を変える行動です。「実」は旧字で「實」。字の形は神社の建物のなかに供え物がある状態で、大事なものという意味を持ちます。「践」は旧字で「踐」。薄いものを重ねる状態に足がつく、つまり足跡を意味します。「實踐」とは大事なものを抱えて歩き続ける状態を表しているのです。

万人幸福の栞に「理屈無しで行って下さい。」とあります。理解してから行ったのでは遅すぎるという意味です。純粋倫理とは一般(旧)道徳と違い、人間のみならず万物を対象としています。つまり自然の法則に従った道徳であり、これは形よりもむしろ心の在り方を問題とします。イヤイヤやるのか、喜んでやるのかで結果が違ってくる「心の生活法則」です。小さな苦難を大事にしましょう。的外れなこと、しかたなくイヤイヤ、結果ばかり気にするといったことは実践ではありません。長く倫理活動を行う人の中に、「やってるつもり」になりがちな人がいます。実践を行っているつもりが、ただの習慣になっています。実践とは習慣を壊すこと。「わかってはいるけどなかなかできない」はやりたくないだけ。
倫理法人会が普及拡大から、拡充に路線変更をして3年目になります。見失われがちになる実践を大事にし、それに伴う体験を拡充につなげていきましょう。